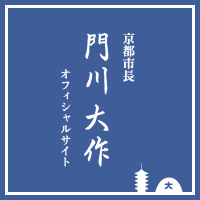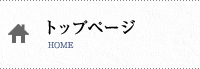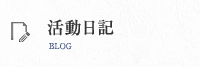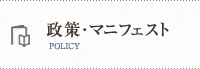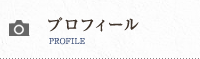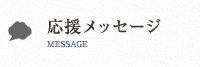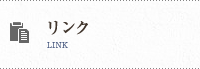2009/08/16
祖先に想いを馳せながら 五山の送り火
(鳥居形松明保存会の皆さんと)
(炎天下、鳥居形松明保存会の皆さんと薪を運びます)
(船山で護摩木を書きます)
東山如意ヶ嶽の「大文字」、松ヶ崎西山・東山の「妙・法」、西賀茂船山の「船形」、金閣寺付近大北山の「左大文字」、そして嵯峨曼荼羅山の「鳥居形」。
16日の夜、夏の夜空にくっきりと浮かび上がる「五山の送り火」は、京都の夏を彩る風物詩のひとつです。
今日は朝から、嵯峨曼荼羅山へ。続いて西賀茂船山へ。
弘法大師が石仏千体を刻んで、その開眼供養を営んだときに点火したことが始まりとも、伏見稲荷大社のお灯明として焚かれたという説、そして、愛宕神社との関係を重視する説もある鳥居形。
そして麓の西方寺開祖の慈覚大師が唐留学の帰路、暴風雨を鎮められた故事にちなむとも、疫病が蔓延した初盆の供養に行われたとする説、そして、藁や木で作った舟に水塔婆や供物をのせて流す「燈籠流し」の舟とする説などのある舟形。
連綿と受け継がれてきたその伝統、先人の想い・祈りをひしひしと感じながら、京都の未来に想いを馳せつつ、薪を運び、護摩木を書かせていただきました。